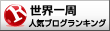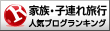5月から始めた連載が14回目になりました。正直、旅だけの話は経験談を多く語ることはできても、このような短い文章の中でその良さやすばらしさを伝えるのは難しく感じている今日この頃です。
今回は、旅の教育についてお話していきたいと思います。
前回並びに今回の旅育については、あくまで私の場合ですが、
1.無理をさせない
2.楽しませる
3.興味を持ったものを深く掘り下げていく
この3つのステップを踏むように心がけています。旅行は楽しく、良い思い出になるだけでなく、色々のことを感じ、伝えられるものだと思っています。人生を豊かにする意味でも、家族旅行をもっとしていきましょう!
※私の子供は小学2年生の長女と幼稚園生の息子の2人です。
我々夫婦は、子供たちにどんな体験をさせているか?
前回もお伝えしたように、私は子供たちにまず旅を好きになってもらうことを大切にしているので、楽しませることを意識しています。したがって、今までになかった経験をさせることも大切にしていますが、プールで遊んだり、美味しいご飯を食べたりといった、旅の楽しさを感じてもらうことをまず念頭に置いています。
その上で、一番重要視していることは、
「自分でやりたいと言い出したことをやってみてもらう」
ことです。
子供たちは、やってみたいことを「やりたい」と探してくることもあります。また、私や妻が面白そうなことや楽しそうなことを見つけ、「やってみる?」と聞いて「やる」と言われれば、いくらでもやってもらいます。「やらない・やりたくない」と言われれば、その時は無理にやらせません。
やりたくないということは、嫌いな食べ物を残すといったこととは意味が違います。世界中でここでしか体験できないということであっても、嫌々やってトラウマにでもなればそれこそ意味はないと思いますので、常に本人たちの意思を尊重するようにしています。
下の子はまだ幼稚園生ですが、やりたいこと・やりたくないことはきちんと自己決定しますし、自分なりに考えてくれていることは、親にも伝わってきます。

ケニアにてマサイ族の踊りを体験中の娘。楽しそうに異文化体験
動物とのふれあいで心の教育を心がける
まだ子供たちが小さいということもあり、家族海外旅行では動物とのふれあいを計画の中に入れるようにしています。マレーシアではオランウータンとふれあい、バリではゾウに乗り、沖縄ではイルカを実際に触ったこともあります。
「イルカって触ると固い!」
「オランウータンの赤ちゃんかわいい!」
「馬とゾウって乗り心地が全然違う!ゾウさんは乗るの疲れる・・・」
動物とふれあうと、子供たちは感じたことをストレートに表現し、記憶してくれます。幼い子供たちにとっても、動物とのふれあいはかなり刺激になっているようです。
動物とのふれあいは心の教育にもつながりますし、人と動物の絆というのは子供の成長にかけがえのないものと思っています。アニマルセラピーの効果は有名ですが、ペットとのつながりが教育に良い影響をもたらしている可能性を示した研究1)のような報告もあるようです。
誠に自分勝手ですが、私たち夫婦の場合はペットがいると長旅がしにくいという懸念から、自宅での生き物の飼育は昆虫くらいしか出来ません。したがって、外では可能な限り、子供たちに動物とのふれあいをさせてあげようと心がけています。日本国内はもちろん、世界各国のいろんな動物を見たり、触ったりしております。

バリにてゾウの餌やり体験。ゾウの食べ方を詳しく観察していて、その様子を教えてくれていました
子供たちが文化の違いを感じ取った「アザーン」の体験
今年の夏、アフリカのザンジバルというイスラム教の影響が強く残る土地へ訪れましたが、そこで礼拝を知らせる「アザーン」を聞く機会がありました。
イスラム教徒は1日5回の礼拝をおこなう習慣があり、この礼拝への呼びかけをアザーンといいます。よく、「コーランが流れている」と勘違いされることもあるのですが、別物です。街中に伝わるような放送を流すのですが、特に朝や夕方の礼拝時には、信じられないほどの爆音でアザーンを流す国も多くあります。
感覚としてはライブ会場が家の横にできたくらいの感覚です・・・。子供たちは、なんでこんなにうるさいのか、どうしてこんなことをするのか、とても興味を持ったようでした。
そこで私たちは、礼拝の仕組み、アザーンにまつわる我々夫婦の知識・記憶、ムスリムの礼拝の仕方など、自分の見てきたものを伝えると同時に、you tubeなどでイスラム教についての知識を一緒に見たり聞いたりして学ぶことによって、文化の差を面白いと感じ取ってもらうように心がけました。
子供たちにとって、初めて聞く・知ることは非常に興味深かったようで、「アザーンっていうの日本では聞けないんだよね~面白かったなあ~また聞きたいけど、うるさいよねえ・・・」と娘はしっかりと心に刻んでいたようです。ただ、息子は「目覚まし時計」としか認識していなかったようで、小学生の女の子と幼稚園児の差かなあと、そこも親心としては興味深かったです笑。
ザンジバルにて。この街で響き渡るアザーンは子供には衝撃的だった様子。
まとめ
こうして考えると、どこの国でどんな体験をするのかは、お子さんの性格・年齢・環境などによっても大きく違うと思います。
動物とのふれあいは子供たちにとってもわかりやすく、そして親しみやすいものです。しかし、やはり外国に行ったからには、文化の違いを体験してもらうことを心がけています。言葉の違いはもちろんですが、生活習慣の違いで興味を持ったものを少し追及して教えたり、一緒に調べたりして学ぶように心がけています。
私は世界中をこの目で見てきて、ぜひ子供たちにも旅を通じて世界の広さやすばらしさを知ってもらうとともに、厳しさ・儚さなども学び、人生の糧としてほしいという強い想いがあります。もともと教師になることも考えていた私にとって、どうやって旅を通じて成長していってもらうか、それが課題であり、常に考えていることです。そのことを記事にしてみました。旅好きな子を育てるには?も併せてご覧いただけると嬉しいです。
多くの方がお子様方に海外体験をさせたいと思うかもしれませんが、焦りすぎず、無理強いせずに、異文化の楽しさ・面白さを体験させてあげてほしいと思います。
次回は旅にまつわる「コミュニケーション」の問題です。旅で得たコミュニケーション能力は教育にも関係するかもしれませんが、医者になっても非常に有用であった経験について、述べていきたいと思います。
【参考文献】
1)Purewal R, Christley R ,et al.:Companion Animals and Child/Adolescent Development: A Systematic Review of the Evidence. Int J Environ Res Public Health. 2017 Feb 27;14(3)
!ポチお願いします!
![]()
にほんブログ村